お子様の誕生は、人生最大の喜びの一つです。
しかし、同時に教育資金という大きなテーマに直面します。
多くの方が最初に検討するのが「学資保険」ではないでしょうか。
しかし、このブログ「準富裕層からのFIRE」では、
これまで一貫して学資保険はムダであると主張してきました。
なぜなら、学資保険という「守りの金融商品」では、
現代の経済環境で必要な教育資金を効率的、
かつ柔軟に準備することができないからです。
本記事では、過去の記事の内容を踏まえ、
学資保険が時代遅れである決定的な理由を改めて解説し、
準富裕層を目指す私たちが実際に採用している、
新NISAを活用した教育資金の賢い作り方を徹底的に解説します。
なぜ「学資保険はムダ」なのか?3つの決定的な理由
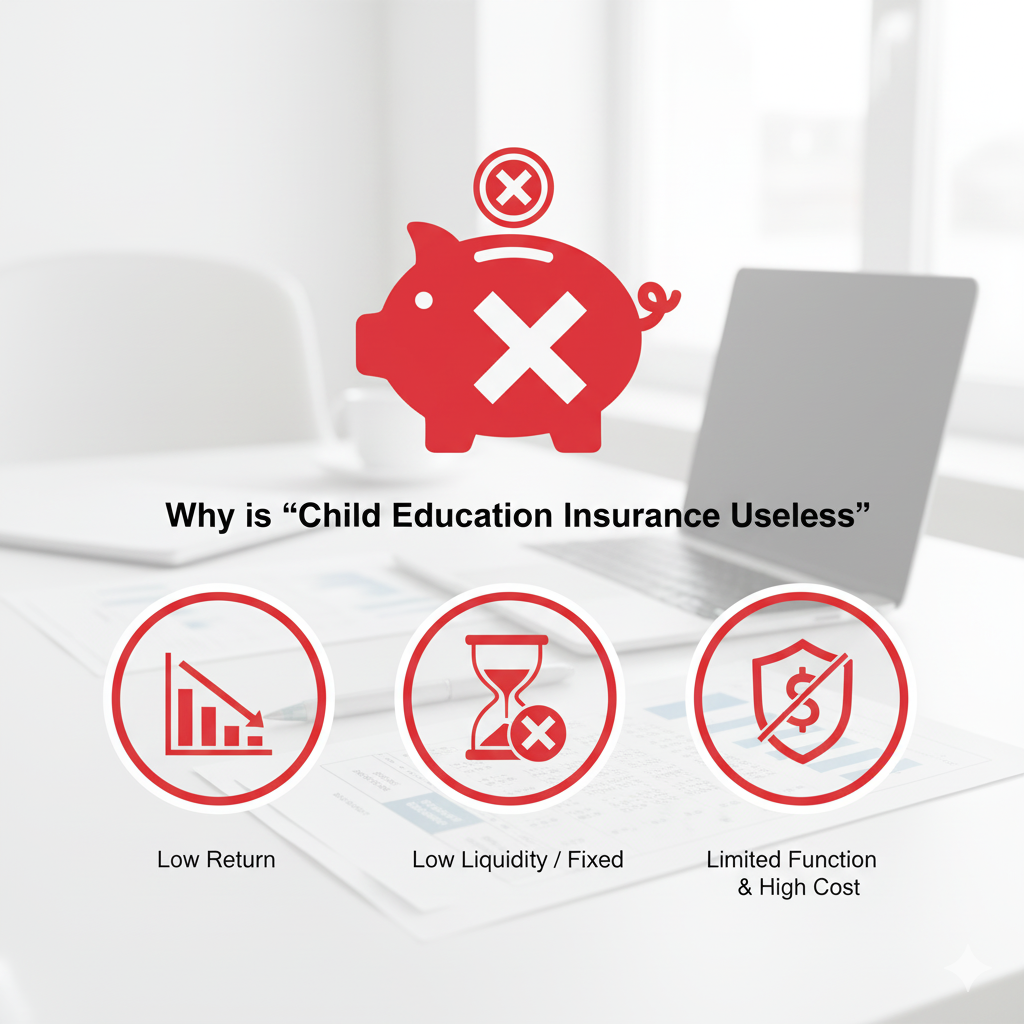
学資保険がムダである最大の理由は、
その低すぎるリターンと硬直性の高さにあります。
特に、金融資産5,000万円以上を目指す準富裕層にとって、
学資保険は資産効率を大きく低下させる要因になりかねません。
1. 実質的な利回りがインフレに敗北している
現在販売されている学資保険の多くは、
返戻率が105%〜108%程度です。
これは、100万円を支払っても、
満期で戻ってくるのが105万円から108万円にしかならないということです。
これを年利に換算すると、積立期間や商品にもよりますが、
年利0.2%〜0.5%程度という極めて低い水準になります。
- インフレ率との戦い: 日本銀行が目指すインフレ目標は年率2%です。実際、直近では食費や光熱費などの物価が大きく上昇しています。もし今後18年間で平均インフレ率が1%や2%になった場合、学資保険で増えたわずかなお金は、物価上昇によって実質的に価値が目減りしてしまいます。
- 機会費用(Opportunity Cost)の損失: もし同じ金額を年利5%で運用できるインデックスファンドに投資していた場合、得られたはずの利益を放棄していることになります。この「得られたはずの利益」こそが、学資保険がもたらす最大のムダなのです。
2. 資金の流動性が低く、ライフイベントに対応できない
学資保険は、原則として満期までお金を引き出せない硬直性が問題です。
- 途中解約リスク: 契約途中で急な出費やライフスタイルの変化(マイホーム購入、転職など)で現金が必要になった場合、学資保険を解約することになります。ほとんどの場合、途中解約では元本割れを起こし、大きな損失を被ります。
- 教育資金の多様化: 昔と違い、教育資金の使い道は画一的ではありません。留学費用、専門的な習い事、大学院進学など、必要となるタイミングや金額が多様化しています。特定の年齢(15歳、18歳など)に固定された給付金では、柔軟な資金ニーズに対応できません。
3. 「保険」としての機能が限定的で高コスト
学資保険には「契約者に万が一のことがあった場合、その後の保険料の支払いが免除される」という保障機能が付帯しています。
- 保障機能の代替: この機能は、既に加入している定期保険や収入保障保険で代替可能です。学資保険は、この低利回りな積立部分と、代替可能な保険部分がセットになっているため、高コストで非効率な商品になってしまっています。
- 本質的な役割: お金を増やすことは投資の役割であり、万が一に備えることは保険の役割です。この2つを混ぜてしまうと、どちらの機能も中途半端になってしまうのです。
準富裕層が実践!新NISAを活用した教育資金戦略

ムダな学資保険をやめ、私たちが取るべき戦略はシンプルです。
それは、「非課税投資制度」を最大限に活用し、時間を味方につけて資産を増やすことです。
ステップ1:目標額を「見える化」する
まずは、目標とする教育資金の額を明確にします。
| 進路 | 必要時期 | 準備目標額(目安) |
| 高校卒業まで | 18歳まで | 500万円 |
| 私立大学理系 | 18歳〜22歳 | 500万円 |
| 合計目標額 | 18年後まで | 1,000万円 |
※上記は一般的な目安です。公立・私立、文系・理系、自宅通学・下宿などで大きく変動します。ご自身の目標額を設定してみてください。
ステップ2:新NISAの「つみたて投資枠」で毎月積立を行う
教育資金は、目的が明確な長期の目標です。
この目的に最も適しているのが、新NISAの「つみたて投資枠」です。
| 運用目標 | 新NISAの活用法 |
| 目標金額 | 1,000万円(18年間) |
| 目標利回り | 年率5%(保守的な想定) |
| 毎月の積立額 | 約2.8万円 |
年間約33.6万円の積立で、18年間で合計の投資元本は約605万円になります。
年率5%で運用できた場合、目標の1,000万円を達成できる計算です。
新NISAのつみたて投資枠(年間120万円)は十分な余裕があるため、
他の生活防衛資金や老後資金の積立と並行して、この教育資金の枠を確保しましょう。
投資すべき商品:全世界株式かS&P500
教育資金のように絶対に失敗できない長期投資では、
以下の2つのいずれかを選ぶのが最適解です。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500): 過去実績で高いリターンを誇る米国経済の成長に投資します。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー): 世界経済の成長全体に広く分散投資します。特定の国に依存しない安定感が魅力です。
どちらも低コストで、私たち準富裕層が老後資金でも活用している王道の商品です。
ステップ3:資金の引き出し時期と方法を決める
教育資金の積立には、出口戦略が非常に重要です。
- 使用時期の分散: 大学受験の資金は18歳ですが、その後の在学中の授業料は22歳まで毎年必要です。資金のピークは18歳ですが、慌てて全てを引き出す必要はありません。
- 「生活防衛資金」への移動: 子供が高校3年生(17歳頃)になったら、運用中の教育資金の一部をリスクの低い資産(例:円定期預金やMMFなど)に移動させることを検討します。これにより、受験直前に市場が暴落しても、必要な資金は守ることができます。
- 必要な分だけ売却: 授業料の支払いが近づいたら、必要な分だけを都度売却(換金)し、残りは引き続き非課税で運用し続けるのが理想的な方法です。
40代子育て世代のための実践Q&A

教育資金の準備にあたり、子育て世代の方々からよくいただく疑問にお答えします。
Q1:新NISAの非課税枠を教育資金で使い切ってしまっていいですか?
A. 最高の使い道の一つです。
新NISAの非課税枠(生涯1,800万円)は、老後資金だけでなく、教育資金のような人生の大きな出費のために使われるべきです。教育資金は10〜15年程度の期間で運用した場合、非課税の恩恵を十分に受けられます。教育資金で非課税枠を一部消費しても、残りの枠で老後資金を準備する時間は十分にあります。
Q2:教育資金と老後資金の口座を分けるべきですか?
A. 分けることを強く推奨します。
- 老後資金の口座(長期・高リスク許容): 60歳まで絶対に手をつけない資金。全世界株式やS&P500に全額投資。
- 教育資金の口座(中期・目標年限あり): 18歳までに使う資金。こちらも全世界株式やS&P500に投資するが、目標時期が近づいたら安全資産へ徐々に移動させる。
口座を分けることで、それぞれの資金の目的とリスク管理を明確にし、心理的にも混同を防ぐことができます。
Q3:暴落が来て、必要な時にお金が減っていたらどうすればいいですか?
A. それを防ぐのが「出口戦略」です。
暴落リスクを回避するために、先述の通り、資金が必要になる3〜5年前から段階的にリスクを減らす行動が重要です。
- 15歳(高校入学時):教育資金の1/3を現金化または低リスク資産へ移動。
- 17歳(受験期):教育資金の残り1/2を現金化または低リスク資産へ移動。
このように、必要な資金を事前に確保しておくことで、市場の暴落に左右されず、安心して大学費用を支払うことができます。
まとめ:賢く増やし、FIREに近づく
学資保険は、銀行預金よりもマシですが、
私たちの目指す準富裕層からのFIREという目標から見れば、資産効率が悪すぎる商品です。
子育て世代の資産形成は、「新NISA」を活用して、
全世界株式やS&P500などのインデックスファンドを長期・積立・分散で運用することが最適解です。
お金のムダを省き、賢く増やし、ご自身のFIREへの道を加速させましょう。
この記事が、あなたの教育資金準備の一助となれば幸いです。














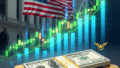
コメント